
|
証明の基準、承認方法等について検討している。
(1)Departure Clearance関連の基準として、次の様なものが有るが、何れもが、現在未完成である。
*EuROCAE ED78 WG45の報告、
*FAA Oceanic Safety Assessment、
*ISPACG OPeration Procedure,Ver.4.0、
*ICAO SARPs、
(2)安全性と共通性に関する要件の検討・調整チームを設けて、次の事項を検討している
*耐空性証明の技術的な承認事項
*運用上の承認事項
*ATSに使用することの許認可
これらを検討するに当たっては、ボーイング社のこれまでの経験をも参考にして進めている。
(3)承認された基準(ドキュメンテーション)が必要
1SPACGに於いては、関係CAA、航空機製造者、通信サービスプロバイダ、IATA、ICAO、IFALPA、IFATCA等々が参画し、システムの導入についてその基準が作成・承認されて来た経緯がある。
しかしながらDGACを中心とした共同検討チームは地上の関係者のみであり、今後、ARINCSPEC−623の導入に向けて、航空機製造者、航空会社等の協力を得ることが必要である。基準の完成を1996年10月を目標としている。
3.1.1.2.3.1.3 フランスのデータリンク導入に関する考え方(Mr.Patrick Souchu,DGAC/STNA)
(1)ATSデータリンク・サービス⇒CPDLC,ADS
(2)標準⇒AMCP,SICASP,ATNP,ADSP等のICAO勧告を中心に標準化を進める。
(3)どのデータリンクを導入するか
a.すぐに導入可能なのがACARSである。ネットワーク、航空機側装備があるが、制約もある。
b.ATNの導入がこれに続く。欧州のコア・エリアではサブネットワークとしてVDL MODE−2及びSSR MODE−S Enhancementが使用される予定。
(4)経費効果⇒検討されなければならない。
(5)リスク管理⇒リスクの存在の可能性を識別し、取組むべき事項の認識。
(6)導入のシナリオ⇒DGACとして、次のような一覧表を作成して、どの様なサービスが、どの様に展開されて行くのかが一目で判るようになっていた。
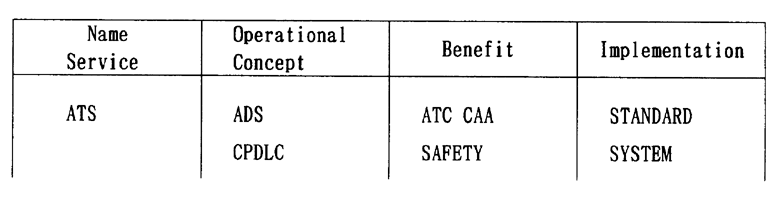
前ページ 目次へ 次ページ
|

|